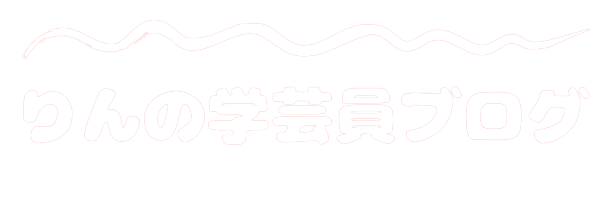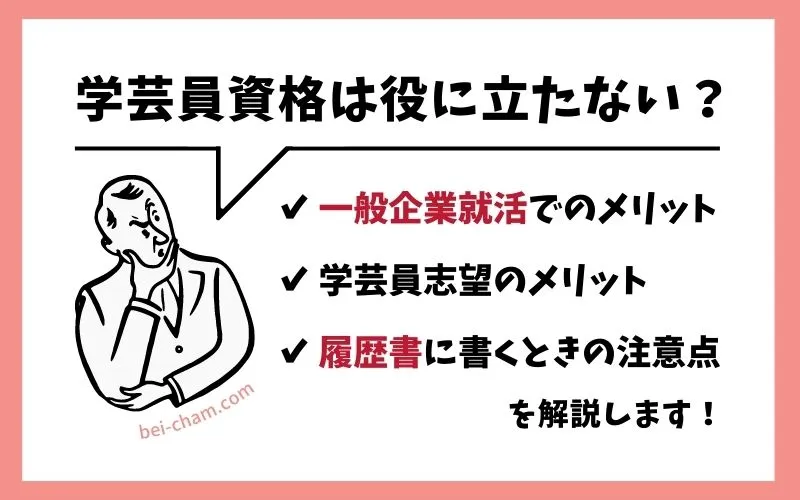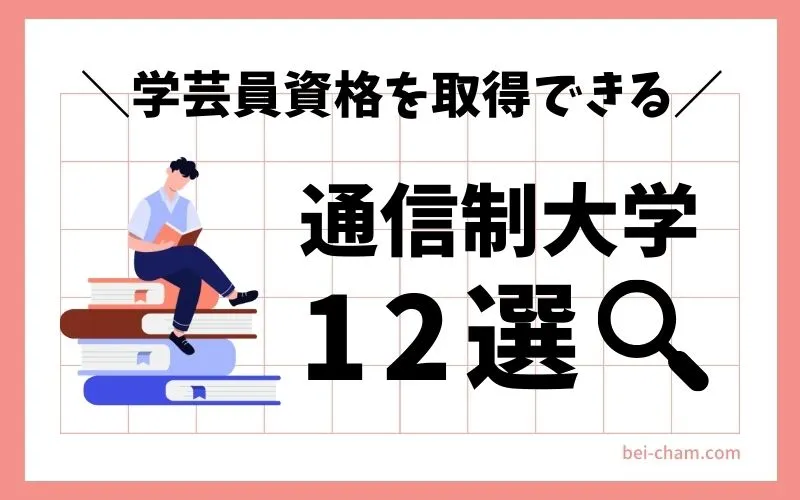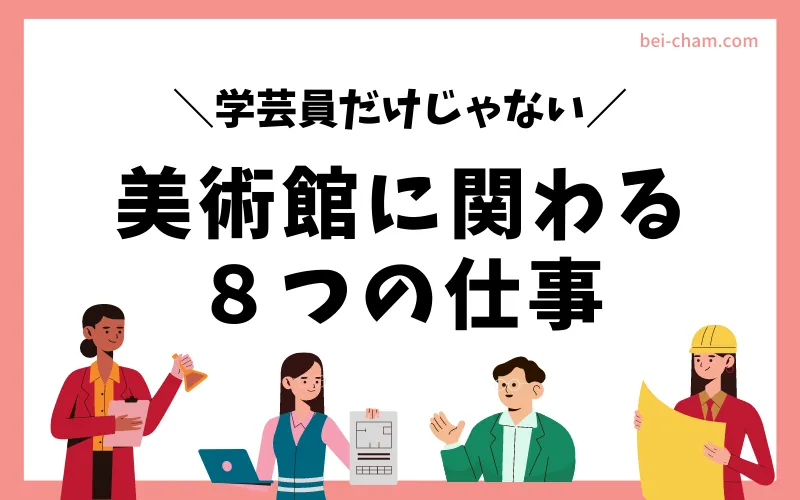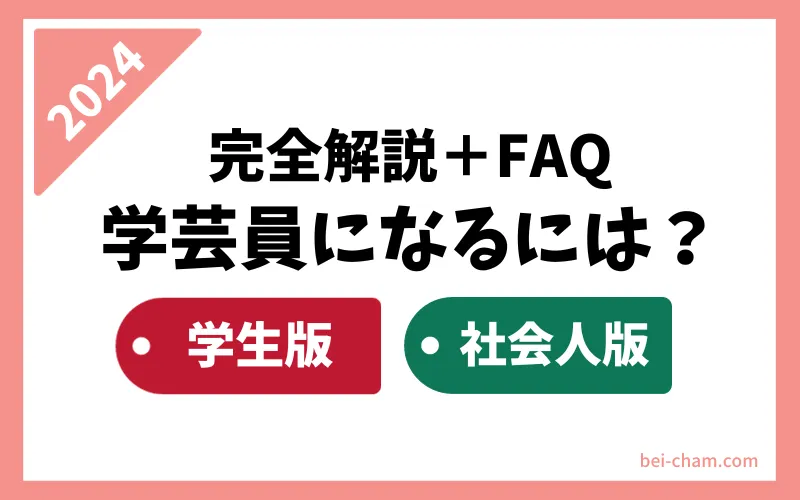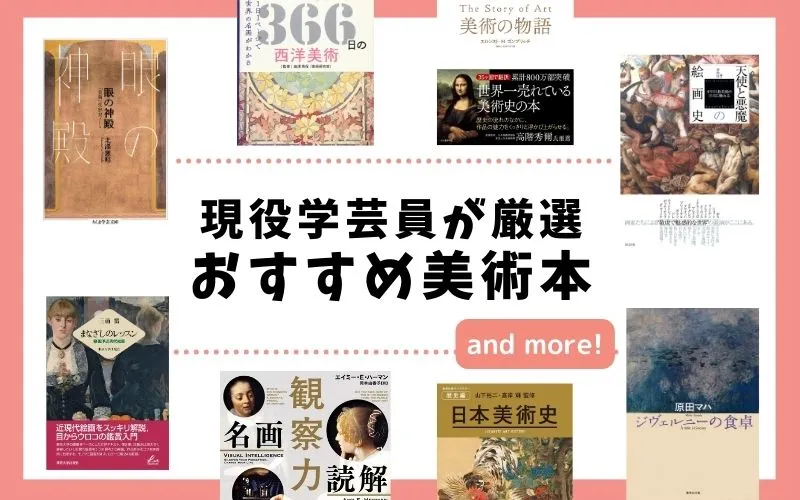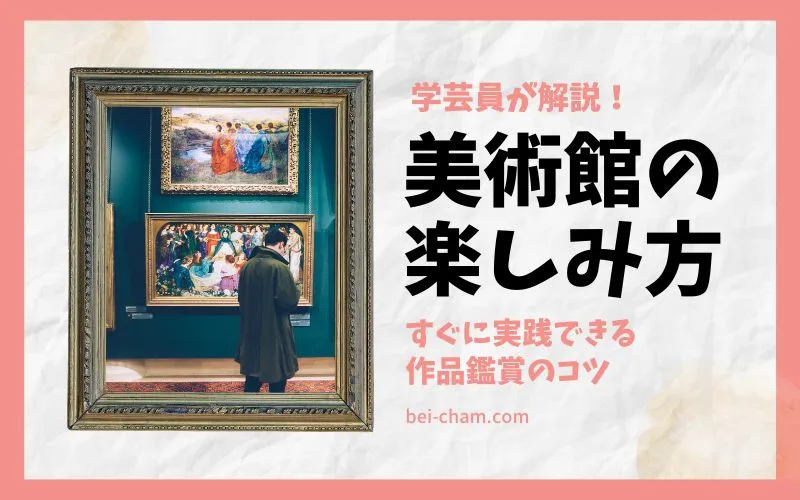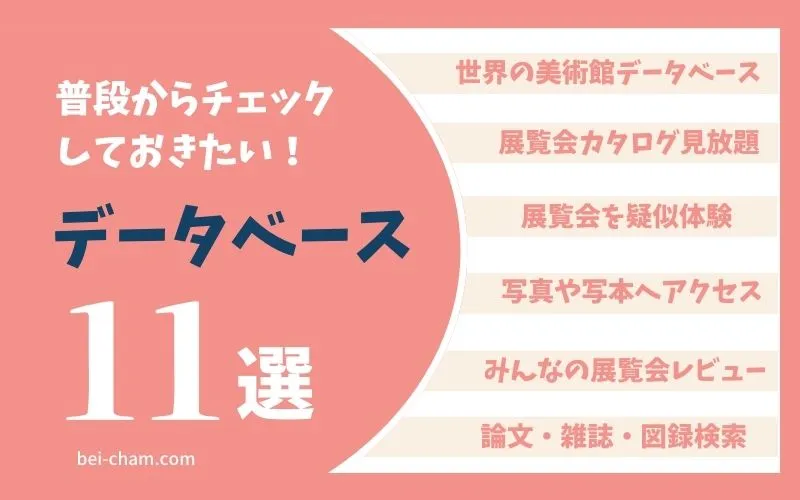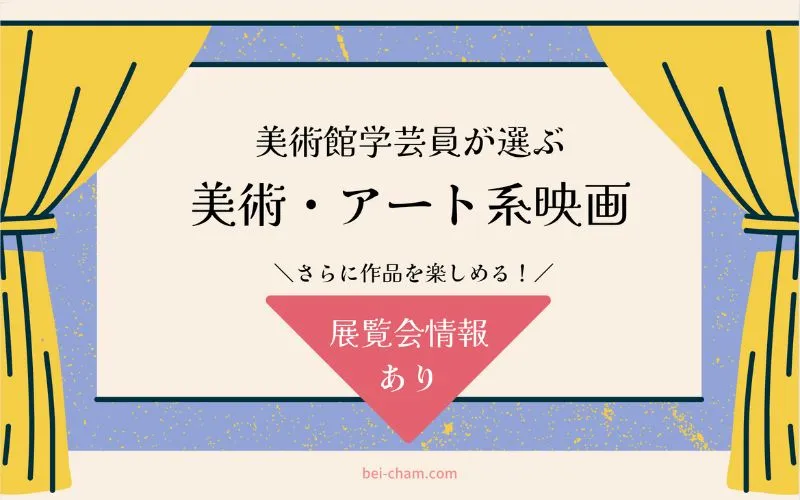筆者について

現役学芸員のりん(@rinhwan_blog)です
- 正規雇用の美術館学芸員
- 大学在学中に学芸員資格を取得
- 一度は一般企業で就活&内定
→最終的に大学院に進学、美術館学芸員採用
本サイトでは、学芸員を目指していた頃の自分が知りたかったこと等を紹介しています
以下のように考えていませんか?

学芸員資格は役に立たないって本当?

学芸員資格を一般就活にも役立てたい
せっかく取得する資格です。
正直なところ学芸員になる以外にも役立てられるに越したことはありませんよね。

この記事では、実際に私が資格取得課程を経て良かったと思う点や、就活で学芸員資格を売りにしたい場合の注意点を紹介します
学芸員資格を使って一般企業に就職したい方も、学芸員になりたい方も、学芸員資格を取得しようか迷っている人も是非参考にしてみてください。
※博物館学芸員資格の取得方法については、こちらの記事内で解説しています。
博物館学芸員資格は役に立たない?取るべき?
学芸員になりたい気持ちが「ゼロ」の人は、取らないほうが良いです。
博物館学芸員資格は、一般企業就活で強烈なメリットになるような資格ではありません。
逆に学芸員への道を少しでも考えている人OR学芸員ではなくても美術系の就職先を狙っている人は、取得して損はないと思います。
理由としては以下のような点が挙げられます。

では、具体的にどのようなメリットがあるのか考えてみましょう
博物館学芸員資格のメリット【学芸員志望】
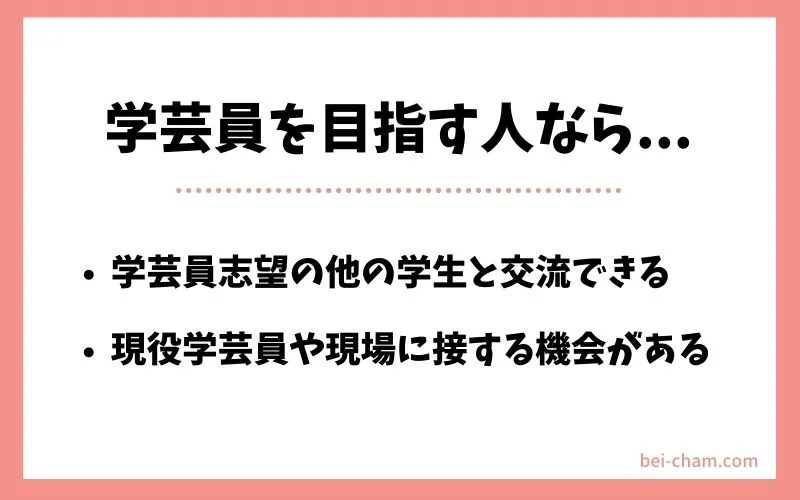
学芸員採用へ応募できる以外に、博物館学芸員資格取得にはどのようなメリットがあるでしょうか。
学芸員志望の他の学生(先輩)と交流できる
「学芸員志望の他の学生と繋がりが持てる」というのが、1番大きいメリットではないでしょうか。

特に文学部以外の人には、生命線とすら言えるかもしれません
筆者は文学部に所属していませんでしたので、学芸員を目指す友人は周りにいませんでした。
つまり学芸員就職以前に、そもそも大学院進学にはやや不利な状況。
他学部にいると、文学部にいれば入ってくる情報(研究計画書や院入試の過去問、院研究室の雰囲気、学芸員就職口の数、教授と美術館の関係性など)にアクセスすることが非常に難しいのです。
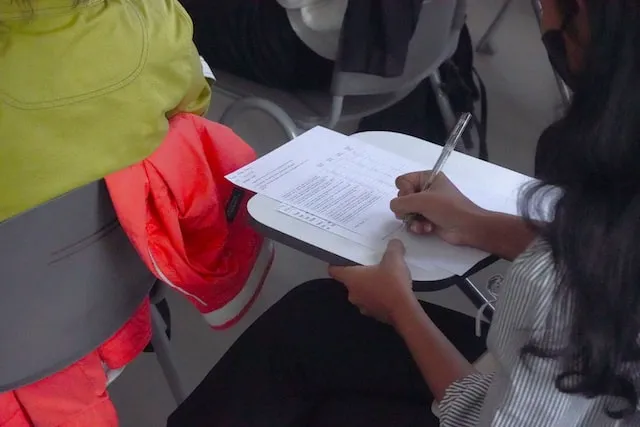

そこで助けられたのが、学芸員課程の授業!
文学部の学生や既に研究室に在籍している院生、学芸員を目指す同期などを知り合うことができ、一気に情報が流れ込んできます。
グループワークなども多いので、仲良くなりやすい環境です。
私は授業で一緒になった先輩に、このあと数年ずっとお世話になりました。
大学院入試の準備からサポートをしてくれ、研究室で励まし合い、そして今はお互い学芸員として一緒に仕事をする仲です。

私の場合、この先輩との出会いがなかったら、学芸員への道はかなりハードになっていたと思います
博物館実習で学芸員や現場に接する機会がある
授業のほとんどは座学ですが、目玉はなんといっても博物館実習!
学内に博物館相当施設が併設されている場合は、博物館への申請や挨拶、バックヤードツアーなどがないことがほとんどです。
なので、外部の博物館で実習させてもらえる人はラッキー!
館にもよりますが、期間は1週間〜10日程度程度になります。
実際の作品を使用して展示作業をさせてもらえたり、収蔵庫での整理のお手伝いをしたりと、学ぶことがたくさんありますよ。

学芸員に直接質問できる、またとない機会です
博物館学芸員資格のメリット【一般企業志望】
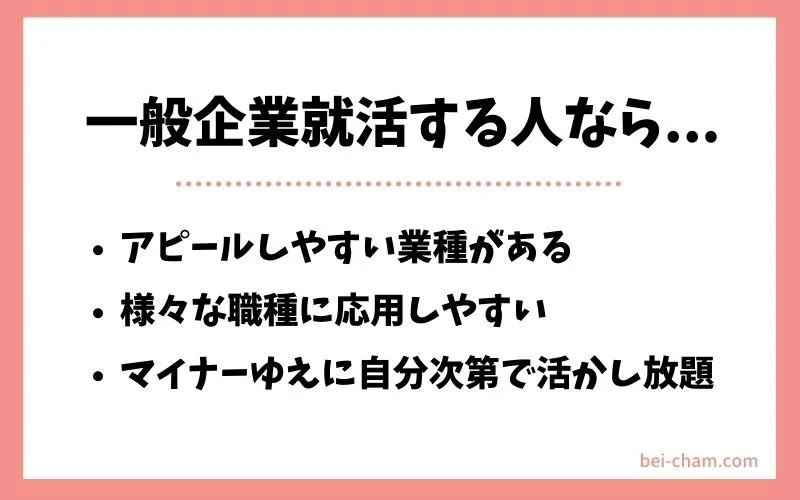
学芸員資格を活かせる仕事は多い
学芸員資格は、企画系や広告、出版系などの企業の場合は、特に活かしやすい資格です。

なぜなら「物事をキュレーションする」という側面のある資格だから
学芸員資格取得過程は、作品の魅力をどう伝えるか、文章を通して情報をいかに正確に伝えるかなどを学ぶ場です。
「企画や広告に興味がある」なんて一言でいっても、「ものをどう魅せるか」学ぶ学芸員資格があることでベースの説得力が増します。
筆者は美術館運営の財団や、展覧会企画の一般企業、出版社などに内定をもらいました。
履歴書にも「学芸員資格」を記載していましたが、いずれも企業の面接でも話題に上がる項目でしたよ。
マイナーゆえに自分次第で活かし放題
人事も学芸員資格について詳しく知らない場合がほとんどですので、学芸員資格というのは言い方次第でかなり「盛れる」資格であるとも言えます。
取得する大学によって授業内容(特に博物館実習)はかなり異なるので、そこまでつっこまれる可能性もありません。
また、同じ資格を持っている人も少ないので印象にも残りやすいです。
学芸員資格を履歴書に書く際の注意点
注意点は面接で「学芸員資格持ってるけど、学芸員にはならないの?」「学芸員は受けないの?」などと聞かれる可能性が高いことです。
これに対する答えは考えておいてください。
場合によっては、「学芸員を目指すのを諦めた人」「うちは保険?」と思われる可能性もあります。「学芸員ではなく御社を選んだ理由」を準備しておくのはマストです。その理由に、学芸員実習での経験などを絡められたら良いと思います。
【まとめ】博物館学芸員資格が役立つ場面は意外にある
いかがでしたでしょうか。
本記事は「学芸員資格」って役に立たなくない?からスタートしました。
結論としては、「学芸員資格が役立つ場面は意外にもある」と思います。

「物事をキュレーションする」という側面のある資格は、大体の職場で役に立つ!
在学生の場合ほとんど追加料金なども発生しませんし、取得も難しくないので、学芸員を目指すか迷っている方は取得するが吉だと思いますよ。